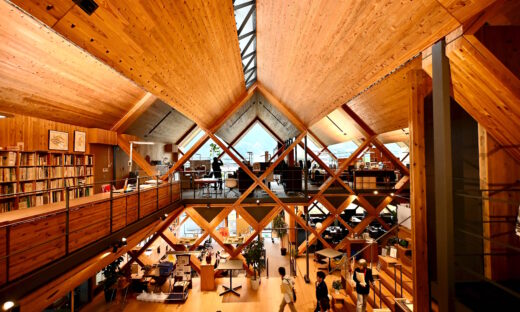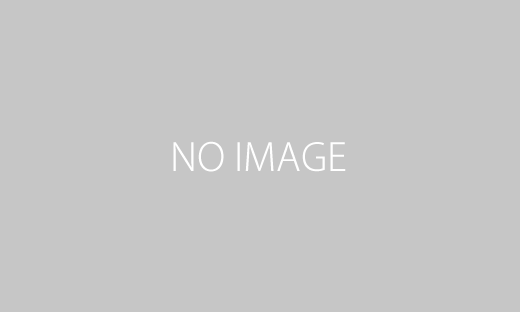【高松支部】防災センター 災害体験+防災講習会(建築士の日事業)

高松支部 防災センター 災害体験+防災講習会
「正しく備え、生き残り、生き続けるために」報告
7月13日に建築士の日の事業として災害体験と防災講習会が開催されました。2024年に能登半島地震、2025年8月には南海トラフ地震臨時情報の発表があり、災害に対する備えがますます重要になってきている中、建築士としてまた一個人の生活者として命を守るために何ができるのかを考え、備えるきっかけにしてもらうことを目的にした企画でした。

始めに訪れた香川県防災センターには、様々な災害を体験できるコーナーがありました。各コーナーでは、防災に関する映像を見て防災の心構えを学び、消火器の使い方、風速30mの暴風や震度7の揺れ、煙を充満させた室内から避難することを体験しました。どれも考えさせられる体験ではありましたが、震度7の揺れを体験する地震体験コーナーが特に印象に残りました。ダイニングキッチンに吊戸棚や食器棚、冷蔵庫などが設置されていて、ダイニングテーブルのイスに座って揺れを体験するものでした。イス以外のすべてのものが固定されていて、テーブルにしがみついていれば何とか持ちこたえることができました。ただ、私の家で同じことが起こったら、何も固定していないので、あらゆる物や食器、ガラスなどが落ちて割れ、避難する際に怪我や障害になる危険が増してくると思いました。災害時に起こりうる危険を想像して、事前に対処することで安全が確保でき、生き残る確率が上がると思いました。
次に場所を、下笠居コミュニティーセンターへ移動して、防災講習会に参加しました。防災士であられる松本建設 代表取締役 松本秀應先生をゲストとして、地震から生き残り、その後の対応や必要な準備についてお話してもらいました。参加者がグループに分かれて、防災センターで体験して気づいたことや考えたことを話し合いました。話し合った上で、実際の東日本大震災や能登半島地震の映像を見せていただき、地震体験コーナーでは15秒の揺れでしたが、東日本大震災の映像を見ると3分ほど揺れていて、次々とモノが倒れていき、避難が困難になっていました。部屋に物が溢れていたり、背の高い収納があったりすると被害が大きくなることを知りました。インテリアや家具の固定について考える必要があると感じました。
最後に、新聞紙で簡単に作れる災害時用スリッパの作り方を教えていただき、新聞紙1枚で少しでも足が守れる工夫があることを知りました。松本先生は、災害に対する知識だけじゃなく、身の回りにあるものを災害時に利用できる知恵を身につけることが、災害を乗り越えていくために必要なことだと教えてもらいました。私の家では、防災グッズは一通り準備しているつもりですが、災害が起こるまでに対処できることを想像し、できるかぎりの備えをこれからも考え続けていければと思います。最後にゲストの松本先生、企画された高松支部の皆様、貴重な体験をありがとうございました。
【青年委員長 藤堂誠司】